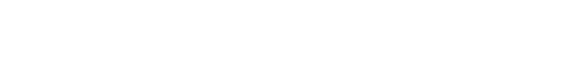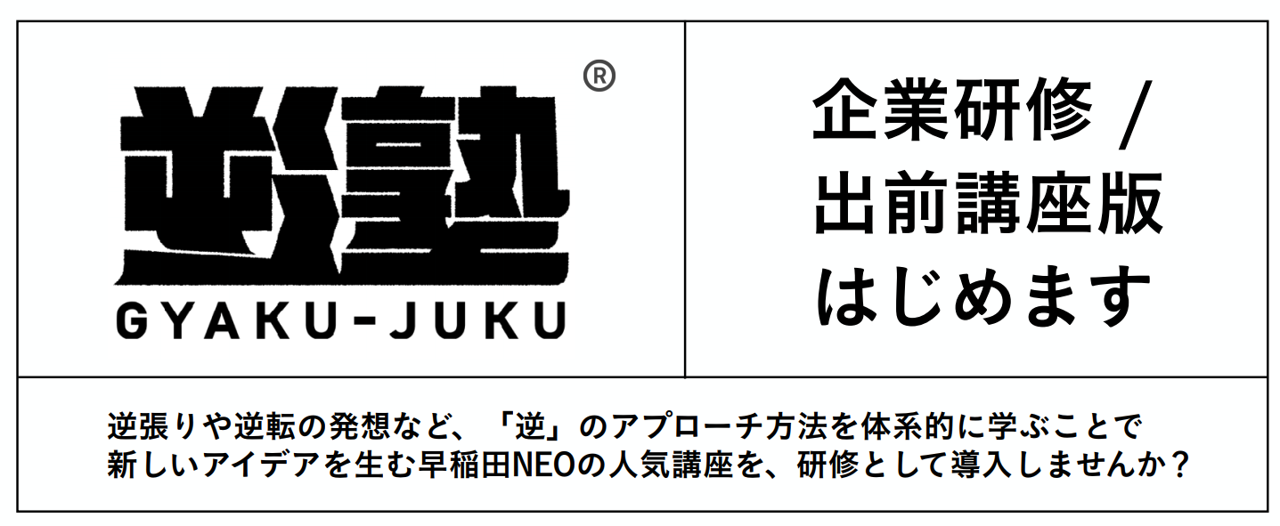「突出」を諦めたとき、「感受」が世界的ヒットを生んだ

2019年5月30日のパイオニアセミナーでは、作家、詩人、歌手として活躍し、早稲田大学第一文学部東洋哲学科のOBでもあるドリアン助川氏をお招きして開催しました。
世界45カ国で映画化され、さらに13言語で出版されるヒットとなった小説「あん」の制作秘話をはじめ、不遇時代の体験から得た、生きる上での大きな気づき「積極的感受」について、お話いただきました。当日のセミナーから一部抜粋して紹介します。
作家・詩人・歌手
ドリアン助川 氏
1962年東京生まれ。早稲田大学第一文学部東洋哲学科を卒業後、雑誌ライター、放送作家などを経て、1990年に「叫ぶ詩人の会」を結成。ラジオ深夜放送のパーソナリティーとして放送文化基金賞を受賞。小説『あん』は河瀬直美監督により映画化され、2015年カンヌ国際映画祭のオープニングフィルムとなる。また小説は13言語に翻訳されている。2017年、小説『あん』がフランスの「DOMITYS文学賞」と「読者による文庫本大賞」(Le Prix des Lecteurs du Livre du Poche)の2冠を獲得。著書に小説『新宿の猫』ほか、第67回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した『線量計と奥の細道』など多数。
|「突出」するためにもがいた不遇の放送作家時代

助川氏の最初の試練は、大学時代の就活だったといいます。学生時代、演劇や芸術に傾倒していたことから、卒業後の進路はテレビ局や映画配給、広告・出版業界を目指すも、色覚異常のハンディキャップがあったため、就職を断念せざるを得ませんでした。そこで、アルバイトをしたり、塾講師をしたりした後、20代のほとんどは放送作家として活動することに。
「放送作家時代は、人気番組だった『アメリカ横断ウルトラクイズ』のクイズを作っていたのですが、12時間ぶっ通しでプロデューサーに怒られながら会議をしていました。ネットがない時代なので、時にはアメリカに電話するなど、徹底的なリサーチが必要でした。テレビ局に出入りしながらも、そもそも映画やエンタメに関しては誰よりも詳しいという自負があったので、何も知らない人に指図されることに不満を抱くことも多々ありました」
フリーランスの放送作家として虐げられるように働き、浮かばれない気持ちを抱いていたという当時の助川氏。虐げられた存在の自分が世間を見返すには、『人より突出した存在にならなければならない』と考えるようになりました。「生涯をかける商売ではない」と思っていた矢先、東欧革命を機に自身にも転機が訪れました。当時を次のように振り返ります。
「東欧革命が起きた翌年、いてもたってもいられず、東欧に取材に行きました。東西ドイツを隔てていたベルリンの壁が崩れ、歴史的変動が起きたわけですが、その後、社会主義国のチェコスロバキア民主化運動も取材し、10万人の市民が広場で肩を組んでビートルズの歌を歌っているのを見て、感動で涙が止まりませんでした。そして帰国後は、革命を目の当たりにしたことで、自分がやるべきことが見えてきた気がしました。」
|伝説のパンクバンド「叫ぶ詩人の会」で一躍有名になるも、さらにどん底の時代へ

その後、パンクバンド「叫ぶ詩人の会」を結成した助川氏。“突出”するために、歌わない歌を表現するスタイルがあってもいいと考えたそうです。その独自の表現スタイルはもとより、金髪で高さ60cmのモヒカンという奇抜なスタイルが話題を呼び、メジャーデビューに至ります。
ところが、バンド活動が軌道に乗り始め、全国ツアーの真っ最中に事件が起こります。メンバーの1人が覚せい剤で逮捕されたことで、すべての仕事がストップ。一夜にして多額の負債を抱えることになりました。
結局、「叫ぶ詩人の会」は1999年に解散。助川氏としては、話題にはなったものの、大きなことができなかった屈辱感がずっと占拠していたといいます。その後、「もっと突出しなければ」と駆り立てられ、ニューヨークへ渡ることに。そこでは日米混成のバンドを結成し、どうにかライブ活動を始めることができたものの、バンドが売れることはなく3年ほどで帰国することになりました。
「40歳で帰国して無職。時代は不況の真っ只中で、3年も経つと人間関係も変わってしまいます。
僕には物語を書くことと歌うことしかできませんでした。道化師の格好をして日本中を歩き回り始めたここからの10年が、本当に一番きつかったです。今年失敗すれば子どもを学校に行かせられないというプレッシャーが重くのしかかり、夜空がしらんでくるたびにひどく落ち込みました。結局、このときまでに僕が“突出”できたのは、ラジオの人生相談のパーソナリティーだけだったのです」
|「突出」が粉砕された絶望の淵から「感受」の必要性に気づいた瞬間

ミュージシャン時代にたまたま出演した人生相談のラジオ番組がヒットし、以後、人生相談の仕事ばかり要求されたことに疲れ果て、人生が落ち込むのをひしひしと感じていた当時。この頃、実は大ヒット小説「あん」につながる出来事と出会ったといいます。それは“突出”したいという思いが見事に粉砕され、並みの生活もままならない状況の下、息詰まるとよく行っていた多摩川の土手での出来事でした。そのときの気づきについて、次のように語ります。
「土手に咲いている花々を見て、ふと人間の『存在』について考えました。存在は肉体として考えがちですが、実は、肉体は最初に出会う他者であり、人生の主体はものを感じたり考えたりする中身にあります。哲学的にいえば、中身が人生の主体となります。意識が“私”の主体なのであれば、夕焼けをとらえている意識はなんなのか。つまり、自分の体を飛び越えて、夕焼けまで意識が届いているわけです。これは禅の発想でもあります。風に揺れるコスモスを見たとき、『あなたは人間界ではたくさん失敗しているかもしれませんが、今、この瞬間、何千というコスモスとつながっていますよ』と言われている気がしました」
このとき、助川氏に「感受」という言葉が降りてきたといいます。大事なのは、徹底的に自分のまわりにある環境をアンテナとして受け止めること。この世に生を受けた以上、自分の目標に向けてひた走ることも大事だけれども、人間1人がこの世でできることはたかが知れていると感じた瞬間でした。
「僕はこのとき40歳で無職ですから、所有することを諦めました。でも、少なくとも今この瞬間、多摩川を積極的に感受して、精一杯感じているわけです。初めから世界は開かれているということに気づきました」
|小説「あん」が映画化され、世界的な大ヒットへ
「突出するべき」ということに体が乗っ取られていたところから、物事を「積極的感受」することの大切さに気づいた助川氏。そこには、徹底的に寄り添う「共感」があったと語ります。この「積極的感受」や「共感」というキーワードが、ハンセン病問題を題材にした小説「あん」のテーマにもつながってきました。
「若い人を集めたラジオの公開録音があったとき、たまたま『社会で生きる意味は?』という質問をみんなに投げかけました。すると、満場一致で返ってきた答えが、『僕たちは社会で役に立つために生きている。役に立たなければ生きている意味がない』というものでした。僕はそれに激しい違和感が湧きました。もちろん有用な人間になってほしいし、それ自体は間違いではありません。でも、戦争が起きれば社会は変わるし、そこに生きることの価値観を丸投げしていいのか、という問題があります。
1953年に制定され、1998年にようやく廃止された悪法『らい予防法』の下では、一度ハンセン病に罹患したら、2度と療養所から出られずに隔離されていました。その後、病気が治っているのにもかかわらず、何十年も隔離されていた人がいる事実が明るみになり、実に人権に反した残忍なことが行なわれていたことがわかりました。そういう人たちに、『社会の役に立たないから生きる意味がない』などとは言えません」
このことから、小説『あん』の構想が生まれました。小説のテーマとして、ハンセン病患者がいかに差別され、人権を無視した隔離生活を強いられていたのか、助川氏は療養所で取材を重ねます。万一、妊娠したら子どもを諦めなければならなかったこと、村八分になり、戸籍も名前も変えられたことで、田舎に帰りたくても帰ることができない人も大勢いました。話を聞くたびに胸がやけどするような思いになり、何度も書くことを諦めそうになったといいます。
ようやく出版にこぎつけると、多くの反響を得て重版となり、やがて河瀬直美監督・樹木希林、永瀬正敏のW主演で映画化されることになりました。カンヌ国際映画祭では、盛大なスタンディングオベーションを受けて、45カ国で上映されることに。書籍は13言語に翻訳され、世界中で出版されました。フランス・アマゾンの外国の世界文学部門では、『アンネの日記』を超えて1位にランクイン。助川氏はパリの大ホールでの講演にも招かれました。
助川氏が「積極的感受」に気づいたことで、小説「あん」のテーマを見出し、作品が映画化されたことで世界中にその想いを届けることができました。その余波について、パリで書籍のサイン会をしたときのエピソードについてもふり返ります。
「劇中、樹木希林さん演じる徳江さんが自分の死期を悟り、生きる意味について残した録音テープを主人公が聞くシーンがあります。原作では手紙を残すのですが、パリで書籍のサイン会をしたとき、このシーンに共感したという、10歳の子どもを亡くしたお母さんが、憔悴しながらもお礼を言いに来てくれました。『息子が死んでから毎日泣いて暮らしていましたが、あなたの小説に出てくる最後の手紙の場面で、息子にはちゃんと生きる意味があったと納得できました』と言うのです。たった10年の生涯だとしても、息子さんは確実に自分で世界をとらえていたわけです。そんな言葉をいただいたことで、ひとつ宿題をやり終えたことを実感しました」
会場では、このパリの母親のエピソードに深く「共感」し、いたるところからすすり泣く声が聞こえてきていました。
|「積極的感受」を実践するためのワークショップ
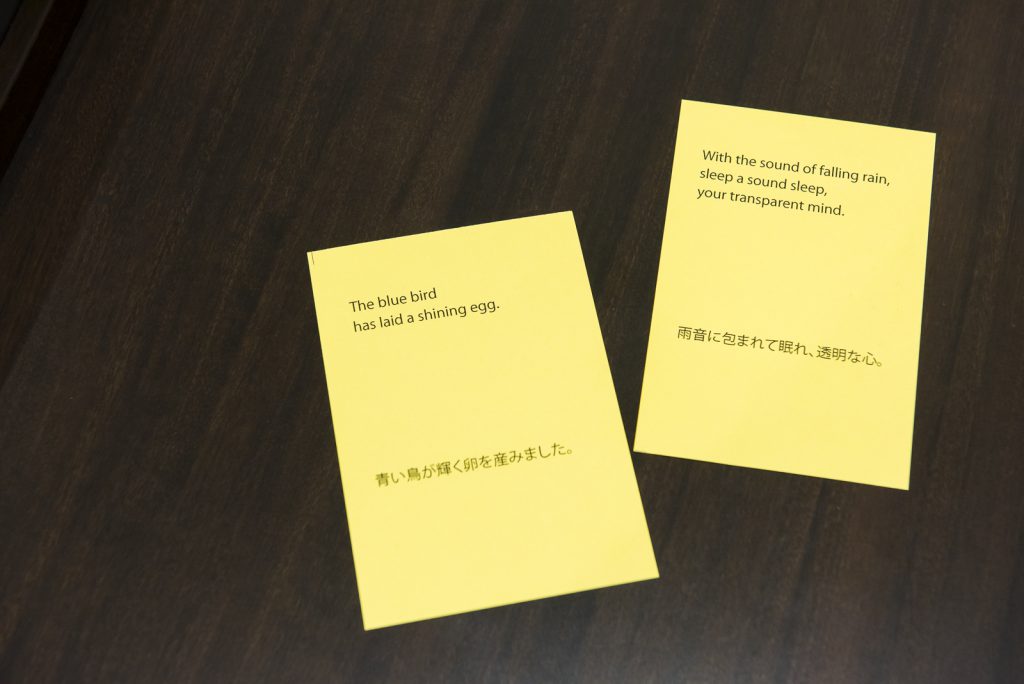
最後に、会全体を通したテーマであった「積極的感受」を具体的に実践するためのワークショップを実施しました。
配布されたのは、助川氏がその日に感じたこと、心象風景を日記に記しているメッセージ。助川氏が都内のビストロで、「箸置きとしてこれらのメッセージを置いておくと、お客さんはどんな反応をするだろう」と実践してみたとき、ある疲れ切った様子の若いサラリーマンが箸置きのおかれた席に座りました。そして、紙に書かれた「Slow and steady climbers never fall」(ゆっくり着実に登る者は決して落ちない)というメッセージに気がつくと、目頭を押さえて泣き始め、その箸置きを持ち帰ったそうです。そのときの経験から、「積極的感受」を実践するためにこのカードを使い始めたそうです。
メッセージの書かれた紙と、もう1枚何も書かれていない色紙が配布され、メッセージを見て受講者それぞれの中に芽生えたなんらかの感情を1行書き、他の参加者の誰かに言葉のプレゼントとして贈るワークを実施しました。
会の終盤には、突出することを目指していた頃への反省から、共感・積極的感受へのシフト、そして大切なことはこれが何かのかたちになっていくためには、何らかの方法で伝える必要性がある、と助川氏は語りました。伝えることによって関係性ができ、関係性ができることによって自分という存在が初めてできてくる、その繰り返しであったと話し、会を締めくくりました。
最後に、受講者の1人が書いたすてきなメッセージを抜粋し、記事を読んでいただいているすべての人に贈りたいと思います。
「目には見えないスピードで成長しているあなた。感じていましたか?」
*
あらゆるジャンルで「競争」よりも「共創」という機運が高まる今、ドリアン助川氏が長い期間を経て体験から会得した「積極的感受」は、多くの人の心を打つセミナーとなりました。
ビジネスに活かせる学びはもちろん、心が震える経験も満載のパイオニアセミナーは、年間通じて定期的に開催しています。詳しくは、こちらをチェックしてください。