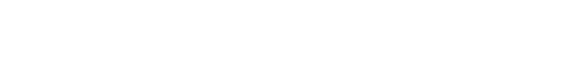実現する組織力~これからのリーダーシップのあり方とは?~

IT技術が加速度的に進歩する今、事業環境が加速度的に変化する今、あらゆる分野の組織にも変化が求められています。
今年最初に開催したパイオニアセミナーにお招きしたのは、県会議員を経て、国会議員や三重県知事を務め、「自治体改革」の先駆者として知られる、早稲田大学名誉教授の北川正恭氏。
県知事時代、「マニフェスト」の概念を提唱し広め、また一方では業務を可視化し効率的にPDCAを回す「事務事業評価システム」を初めて行政に取り入れ、前例踏襲で固定化された業務を変革させた功労者です。
そんな北川氏に、組織を変えるリーダーシップのあり方についてお話しいただきました。
当日のセミナーより、一部抜粋してレポートします。
(プロフィール)
早稲田大学名誉教授、元三重県知事
北川正恭氏
1944年生まれ。1967年早稲田大学第一商学部卒業。1972年三重県議会議員当選(3期連続)、1983年衆議院議員当選(4期連続)。1995年、三重県知事当選(2期連続)。「生活者起点」を掲げ、ゼロベースで事業を評価し、改革を進める「事業評価システム」や情報公開を積極的に進め、地方分権の旗手として活動。達成目標、手段、財源を住民に約束する「マニフェスト」を提言。2003年4月より早稲田大学政治経済学術院教授。2015年3月に退任。現在、早稲田大学名誉教授、早稲田大学マニフェスト研究所顧問。
|政治改革運動に精力を注いだ衆議院議員時代
『地方分権推進法』が確立する以前、衆議院議員だった北川氏は政治改革運動に注力。その後、三重県知事に当選し、地方分権推進を三重県で実現すべく注力します。
冒頭で、今回の話の背景となる、1995年に地方分権推進法が確立するまでの歴史的なターニングポイントについて解説する北川氏。
戦後の日本はGHQ統治下、自然環境を犠牲にしながら工業化が急進し、1970年代には公害が社会問題となりました。
当時、三重県鈴鹿市の市議会議員を務めていた北川氏。身近で起きた集団ぜんそく被害「四日市ぜんそく」の状況を目の当たりにしていたといいます。
「生産が善とされた時代で、工業化が進まなければ戦後の復興はあり得ないとされてました。その後、1970年に初めて『公害国会』が開かれて、さまざまな規制が作られ四日市や川崎が浄化されます。それから約30年経って2001年、ようやく資源循環型を目指す環境国会(環境省の発足)が開かれます。社会のパラダイムが変わるのに30年かかるということを実感しました」(北川氏)
それまで政治の世界で歴史的イベントがたくさんありました。戦後30年後の1975年に、日本は初めてフランスで行なわれたサミットに欧米諸国6カ国のうちの1国として参加します。そしてその10年後には、ドル高の是正が行なわれ、バブル経済の発端となった「プラザ合意」がありました。
「その後の劇的に為替が変動するのを目の当たりにするわけですが、当時表舞台にいらした先輩議員から、いかに行政のトップの決断で社会が影響をうけるのか絶対に忘れるなと言われ、議員としての責任をしっかりと自覚するように指導されました。
そうした時代にわたしは国会議員をつとめておりましたが、1990年代以降は政治改革の時代に突入します。これまで一党優位体制だった自民党に改革が起きて、政権交代が可能な政治にシフトしていきました」(北川氏)
|「地方分権推進法」により、地方自治体に大きな変革のうねり
そして、戦後の政治において後回しにされてきた地方に、いよいよ政治改革の光があてられ、1995年に地方分権推進法が制定されます。これが、その後の地方自治体のあり方を変える大きなうねりとなっていきました。
東京中心で急速な復興・発展を目指した日本は、時代が変わり、気づけば消滅リスクのある地方の街が出てきます。そこで、画一的ではなくローカルに合った多様な政治をとる考え方が生まれました。
そのうねりの真っ只中で北川氏は三重県知事となり、さまざまな改革を実施していきます。
ところが、戦後社会において、それまで国の描いた政策に従うことを求められてきた地方の自治体が、なかなか慣例を越えられずに迷走している姿を目の当たりにすることに。
「初登庁早々、職員に改革案を求めました。すると3人の優秀な職員が改革案を提出してくれましたが、その内容が、明らかに県庁や総務省の方向しか見ていない内容だったので突き返しました。すると、『私たちもそう思っています。でも、とてもできません』と答えるではありませんか」
北川氏が着目したのは、地方分権推進法の条文に書かれてあった「命(めい)によって通知する」の一文。このときの知事としての北川氏の思いが込められたエピソードが印象的でした。
「一体、誰が誰に命令して通知する法律なのでしょう。私は国会議員だったので、各省の事務次官とは通じていました。だからあえて、3人の職員の前で知り合いの事務次官に電話し、『公務員である君が、仮にも公選で県民によって選ばれた知事に対して、“命によって通知する”とはどういうことか?』と問い質しました。すると、傍らでそのやり取りを聞いていた職員は『国に逆らう知事がやって来た』ということで、驚いていました」
国会議員だった北川氏は、地方分権推進法の制定に向けて政治家として働いた経験から、この法律こそ自治体改革のベースと捉えました。
「それまでの自治体は、国の機関委任事務であり、国からの指示・通達を国に代わってするのが仕事で、地方自治体は国のしもべでした。でも、私はそのような古い慣習と決別し、自立した地方社会を実現するために戦うのが知事の使命だと固く誓い、徹底的に自治体改革に努める覚悟を決めました」(北川氏)
|議会に「ダイアログ」スタイルを取り入れ、組織を変える
一方で、県議会議員の経験もある北川氏は、議決機関である県議会と、執行機関の県庁状況との関係性もよく理解していました。県庁関係者が合わせて2万5000人ほどいるなか特に県議会の考え方も変革していく必要性を実感。議員と県庁のなれあいの関係と決別し、県民のために県議会と県庁の緊張した関係をつくりなおすべく真っ向からぶつかる覚悟は決まっていたといいます。実際に、私を敵だとみなす方はいまでも大勢いらっしゃると思います。
「とにかく直接会って直接話す。県議会議員も国会議員も経験済みで、それぞれの体質をよく知っていたこともあり、新しいことを断行し、改革を進めることはそんなに怖くありませんでした。」(北川氏)
議会で「善処します」という曖昧な発言が飛び交えば、「できないことはできないと言え」と叱責したり、「自分のおかげで農道ができた」などといったなれ合いが横行することについても、「そういうのはもうやめよう」と提言したり。どんなに頑固と思われようと、北川氏が徹底的に議会を変えようとする思いの奥には、信念がありました。
「私がつぶれるか、議会がつぶれるかまで覚悟しないと改革はできない。私はつぶれる覚悟がありました」(北川氏)
北川氏は優秀な議長を立てて、執行部を変えるところから手がけました。
「一時期の東京都の議会がどうなっていたかについて、都民は理解していらっしゃったでしょうか。例えば200億円の予算の執行権を都庁が放棄して議会に渡すなんて、そもそも地方自治体の体をなしていません。東京都知事の小池百合子さんが。そこにメスをいれなければ、東京都は変われなかったはずです」(北川氏)
しかし、このように命がけで挑む行政改革や議会との緊張関係、そもそも県民から支持を得るためには、勢いだけではなしえません。自身のこれまでを振り返り、北川氏が「実現」していくことができたのは『ダイアログ』を大事にしたからだといいます。ワークショップを庁舎内や地域住民と話し合っていくスタイルは、三重県が最初に始めたもので、話し合いの上でお互いが納得したら進められる長所があります。
それまでは、たとえば予算を取り合うときに、ほかの部門の悪いところを散々突いて自分たちの部門に予算を取ってくると、優秀なマネージャーだということにみなされてきました。しかし、各部門で足をひっぱりあうのではなく、お互いがめざしていることを理解し、社会をよくしていくように統合していくことで、あたらしい政策が誕生するのです。
ダイアログは、「必要な討論だけど、結論は急がなくていい」というスタンス。それぞれの意見を話し合いによって共有し相対化するというスタイルでした。
|いかに組織内の考え方を変えて発想を広げるか?
昔は自治体に政策を作る権限はありませんでしたが、地方分権推進法が制定されてからは、さにあらず。そこで北川氏が実施した、職員たちの発想を広げる取り組みも実に興味深いものがありました。
「私は職員に『国に言いなりの政策はやめなさい』と呼びかけました。たとえば介護保険制度がスタートしたときに勉強会を開いたら、20代の意欲ある若い職員が集まりました。私ももちろん参加します。参加者は知事の私も含めて平等で、円卓のどこに座ってもOKというフランクなスタイルです」(北川氏)
このとき、参加者全員が10分程度の自己紹介をしたそうです。すると、それぞれの教養が問われるし、北川氏自身もとりとめのないエピソードを話すと、場が一気に打ち解けたといいます。当時を回想し、北川氏が得た結論は、「会社のパラダイムを変えるなら、会議のあり方を変えること」。
|役所には前代未聞の「事務評価システム」を実施
北川氏が貫いたのは、決めたことは徹底的にやり、納得いかないことはダイアログで話し合うスタンス。「1人1人の意識を変えることなく改革はできない」と考え、県庁というパブリックな機関に初めて『事務評価システム』を導入しました。
あるとき北川氏が、「意識改革の提案を集めたらどうか」と総務部長に打診すると、「みんなやりたがらないから、100件集まればいい方」というのが、総務部長の見解だったといいます。
しかしこれまでの一人一人との対話と真剣さを伝えることに注力してきた北川氏のもとに集まった提案は、なんと4500通以上でした。これまで一般職員は役所内にヒエラルキーがあるから、自分の意見が通るなんてあり得ないと思っていたのです。ところが、提案してみたら知事も副知事も読んでくれた、実行してくれたということで、職員たちの意識が変わり始めます。
その2年計画は“生活者起点”を重視した「さわやか運動」。最初は「役所でそんなことを打ち立てても誰もやらない」という意識が根強かったからこそ、体系立ててやるには「理念」が必要でした。
最終的に200項目を作り上げ、それを執行するためにメインに置いたのが、日本の地方行政としては初の『事務評価システム』というわけです。
ところが、1年ほど実施してその失敗に気付くことに。
「そもそも事務事業がどれだけあるか?ということをみんな知らなかったのです。そこで、事業をすべて可視化し、いつまでにどの程度の予算を使って、どの段階まで行けるかということを一覧化して議会に提示し、1年ごとにチェックすることにしました」(北川氏)
失敗要因として北川氏が挙げたのは、優先順位を決めず、小さな事業から手をつけていた点。各政策の優先順位の見極めはボトムアップではできないため、トップダウンでの評価システムに変えるために、6年の歳月を要したといいます。
|組合の圧力が強い県立病院の改革と黒字化に成功
職場の改革の事例として、累積赤字115億円という大変な経営難に陥りながらも、現体制を固持しようとする人達が多かった県立病院にテコ入れしたときのエピソードを北川氏は披露します。
「当時の院長が定年を迎えるにあたり、敏腕の副院長を指名しようとしたら、労働組合から強い反対に遭いました。組合は6000人規模で、そこには改革していく上でどうしても大きな軋轢がありました。、副院長を院長に指名するのに10ヶ月を要しました。わたしも指名を強行したからには、あとにひくわけにはいけません。結果を出すしかないところに追い込まれてしまいます。そんな状況ですが、やはり副院長を信じるしかなかった。とにかく会って話して、対話を重ねました。そうしたら副院長はみごとに応えて病院の収支の健全化を図り、自ら病院の玄関にでて患者に挨拶するなど病院のホスピタリティを高めていく大改革を始めてくれました」(北川氏)
結果、病院は4年がかりで黒字化に成功。病院が自立し、収益が上がったことで、設備投資をはじめ、医療サービスが向上する好循環ができました。
日本は「成長社会」から「成熟社会」となり、「問題」があっても「成長」がカバーしてくれる時代は過去になり、自治体も財源が厳しい時代に。政策の優先度はエビデンスがないと誰も納得してくれないと北川氏は強調します。
「できない理由をのべて実行しないのではなく、実現するための目標を立て結果をだしていくことが重要。そして数値目標を立てたら、県庁のあるべき姿を描いてバックキャスティングすることが必要です。」(北川氏)
最後に北川氏は、次世代の県庁について次のように提言。あらゆる組織にも通じる話に、一同納得させられました。
「今の時代には、アカウンタビリティー(説明責任)が必須。まずはそれを理解しないと県庁は変われないし、激変期についていけません。生活者起点を徹底するために必要なのは、「継続」ではなく「断絶」。昨日とは違う今日を作ることです。行政はある意味安定していてはダメ。もちろん、多くの組織も同じです。今後は、知的労働も別次元にシフトする時代だからこそ、その心構えが必要なのです」(北川氏)
慣例や体制が強固な自治体という組織で、徹底的に改革を進めてきた北川氏だからこそ、その話から聴衆が感じ取ったものは大きく、圧倒的されました。
事業環境の変化に危機感を抱き、組織を変えたいけれど、変われないというジレンマを抱えているビジネスパーソンは多いと思います。そんな人にとって有効なヒントがたくさん詰まったセミナーとなりました。
*
パイオニアセミナーは年間通じ、定期的に開催しています。今後の詳細は、こちらをチェックしてください。