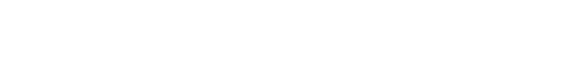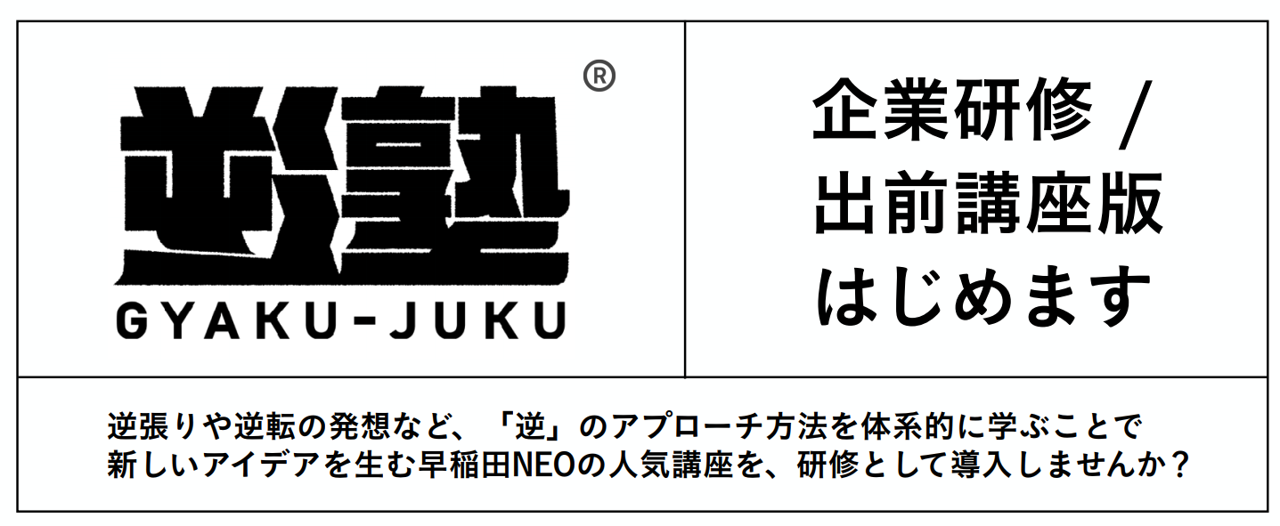理念はシンプルなコミュニケーションで浸透 ~メゾンカイザー成長の軌跡

2019年2月7日に開催したパイオニアセミナーでは、幅広い層にファンを持つフランスパン専門店『メゾンカイザー』を全国展開する、株式会社ブーランジェリーエリックカイザージャポン代表取締役の木村周一郎氏にご登壇いただきました。
講演のテーマは、『結果を生む、メゾンカイザー式“価値合わせ”』です。パン業界において、類まれな成長を見せてきたメゾンカイザーは、いかにして本場フランスの味を日本に広げていったのでしょうか。急成長の裏にあった木村氏と社員やスタッフとのコミュニケーションの問題、そして問題を解決に導いた“簡単な行動”についてもお話をいただきました。当日の木村氏の講演を抜粋して紹介します。
<プロフィール>
株式会社ブーランジェリーエリックカイザージャポン代表取締役
木村周一郎氏
1969年生まれ。慶應義塾大学法律学部卒業後、千代田生命保険相互会社に入社。その後、唯一のFDA(米国食品医薬品局)研究機関である米国立製パン研究所へ留学。ベイキングサイエンスを研究する。ニューヨーク、フランスにて修行を積んだ後、その腕前と経営センスを見込まれ、エリック・カイザー氏の在日パートナーとして、2000年に株式会社ブーランジェリーエリックカイザージャポンを設立。翌2001年、メゾンカイザー第一号店を東京都港区高輪にオープン。2019年現在、東京を中心に、全国で36店舗を展開し、年商40億円、従業員600人超を擁する企業に成長。

|苦しい職人修業は、胸を張って“転職”するため
あんパンで有名な木村屋の御曹司として生まれ育った木村氏は、大学卒業後、生命保険会社に就職します。当時、法人営業を担当し、仕事に生きがいを見出す充実した日々を送っていましたが、入社6年目に退職、家業に戻ろうというタイミングで父が製パン業から身を引くことになったことから転機が起こります。
「あるはずだった家業がなくなってしまい、古巣の保険会社に戻るべきかと考えていたとき、父は『気軽にアメリカにでも行って来い』と言いました。父が指すものは、アメリカのカンザス州にある国立製パン研究所。こちらで基礎化学と発酵を学んできなさいということでした」(木村氏)
その後、ニューヨークで評判のベーカリー『エイミーズ・ブレッド』、そして今や世界10数国に出店するフランス発の『メゾンカイザー』において“完全修業モード”でパン作りを学ぶことになった日々を振り返ります。
「どちらもタダ働きで、とくにメゾンカイザーでは、『毎日パンを3つくれたら、ご自由にコキ使ってくださって結構です』と言いましたら、大喜びで迎えてくれて(笑) 週6日、毎日15時間働きました」
ここまで身を粉にして頑張れた理由を、木村氏は次のように話しました。
「実は古巣に戻ろうかどうしようか悩んでいたとき、生命保険会社でお世話になっていた大手の刷毛(はけ)屋さんが『うちに来るか?』と声をかけてくれたのです。そこに笑顔で迎えていただくためにも、グズグズ言わずにしっかりアメリカで頑張ろうと思いました。渡米・渡仏しているときの目標は、“生命の危機に瀕するぐらいまでは頑張る”でした(笑)」
帰国後、世界的なパン職人であるメゾンカイザーのエリック・カイザー氏が日本で講演をすることになり、お手伝いとして同行することになりました。一緒にいる時間が長くなる中で、気心が知れてくると「日本で店をやらないか?」というカイザー氏のお誘いを受け、現在のスタイルでパン屋を開くことになったといいます。木村氏は、当時の心境を次のように振り返りました。
「そのときまでは、声をかけてくれた刷毛屋に入ろうという目標は変わっていませんでした。ですが、パン屋を職業として考えることに魅力を感じていたのも事実です。そして2000年、メゾンカイザーのパンを日本で売ることを目的とした、株式会社ブーランジェリーエリックカイザージャポンを設立することになりました」
|「正統派フランスパンが売れるわけない」という下馬評を覆す

2000年当時、日本では海軍カレーパンやメロンパンが大ブームで、メゾンカイザーが提供するような正統派フランスパンは絶対に成功しないというのが大方の下馬評であったといいます。その理由は、日本人は噛む力が弱いので、固いパンは受け入れられないから、と。当時はコンビニに並ぶパンも概ねやわらかく、味のついた菓子パンばかりが並んでいました。そのため、製粉メーカーや油脂メーカーなどの関係者は、木村氏に「ソフトフランスパンを作りなさい」と口を揃えて勧めたそうです。そんなチャレンジングな局面で、背中を押される出来事がありました。
「ある日、新橋から横須賀線に乗ると、スルメをしゃぶってお酒を飲んでいる人に遭遇しました。そのときに思いました。『スルメの方がフランスパンより固いぞ』と。また、麻布十番では固焼き煎餅をバリバリとほおばる子どもたちも見ました。そのとき、パリでの光景を思い出したのです。フランスでは実は歯が悪い人が多く、固いパンをコーヒーやスープに浸して食べるのが当たり前だったのです。日本で受け入れられない原因は、アゴの強弱ではない。食べ方を知ってもらう販売をしていないだけだと気づきました」
この単純なことに気が付き、とにかくお金をかき集めて白金高輪に『メゾンカイザー』第一号店のオープンにこぎ着けましたが、当時の白金高輪はタワーマンションも少なく、寂しくて人気(ひとけ)の少ない街だったといいます。結果、惨憺たる売上が待ち受けていました。
「当然のようにパンは売れませんでした。まず、お客様が来ないし、来ても『メロンパンないの?』『ロールパンは?』『何にもない店だな』ということになり、誰もフランスパンには見向きもしません。『ここに欲しいパンはない』とキッパリ言われたことさえあります」
そんなとき、木村氏を支えてくれたのが、前職の生命保険業界での経験でした。「間に合っています」「今、別の保険に入っています」といったお客様のネガティブワードからスタートする商売だった保険業界とフランスパンの販売を重ね、そこから現状を打破するアイデアを考案します。
「お客様に今晩の献立を訪ねることから始めました。たとえば、『肉じゃが、サラダ、白身のお刺身、ご飯とみそ汁』などとお客様が答えます。この献立では、どこにもパンが入り込む要素はありません。ただ、その方は潜在的にパンを買いたいと思っているからこそ来店されているわけです。そこで食材を生かし、パンに合う献立を提案してみました。『肉じゃがの材料はそのままコンソメを使ったポトフにして、白身のお刺身はオリーブオイルをかけてカルパッチョにしてみてはいかがでしょう』と店頭でお勧めしたところ、家族に評判が良かったということで、再びご来店いただくようになりました」
木村氏は「主婦にとって、日々の献立を考えるのは大変な作業であり、とくに主婦を苦しめるのが、“食卓の無反応”なのではないか」と指摘します。そのお客様が木村氏の勧めたメニューを出したところ、いつもの食卓の雰囲気ががらりと変わり、家族から「どうしたの?おしゃれなメニューだね」と言われたそうです。そこで木村氏は、“食卓の無反応”を払拭するべく、『メゾンカイザー』を単なるパン屋ではなく、“パンをフックにしたホスピタリティを提供する場”に変えようと考えました。
方向の転換によって少しずつ客足が伸びていきます。しかし、いつの間にかスタッフとの心の乖離が始まっていました。
|「なぜスタッフはすぐにやめるのか?」を捉えなおす
お店が軌道に乗って評価を得るようになった一方で、スタッフがすぐに辞めてしまうという問題を抱えていた10年前を振り返ります。
「当時、私は1日17時間、週7日間働いていました。当然、心に余裕があるはずもなく、日々イライラしていました。スタッフがダラッとしていたり、気が利かなかったりすると、すぐに苛立ちが募るようになっていたのです。根幹には、『私がこんなに働いているのだから、みんなにももっと働いて欲しい』という思いがあり、それを怒りという形で発散していたわけです。そんな職場の居心地がいいわけがありません。せっかく雇ったスタッフもすぐに辞めていきました」
そんな状況を先輩社長に相談したところ、「給料を払う人と貰う人のモチベーションは違うんだよ」と言われ、目が覚めたといいます。「自分とスタッフは違う人であり、同一視すること自体が間違っていた」というシンプルなことに気が付き、そこから従業員の居心地を第一に考えるようになりました。当時、スタッフが次々に辞めてしまった原因を自身で次のように分析します。
「現場では日々怒ったり、怒られたりが繰り返されます。それは業務上当然の指導であっても、その後に互いに話しかけるチャンスを失ってしまうことはどの職場でもよくあることでしょう。コミュニケーションが途切れて、負のスパイラルに陥ってしまうこともあると思います。これが心のわだかまりになり、退職のきっかけになってしまうのです」
そこで木村氏が考えたのが、“フィジカルコミュニケーション”を行なうことでした。
「部下と握手するだけでもセクハラと受け止められてしまうこともあります。そこで、“グータッチ”を思いつきました。巨人の原監督がやっていたものです。全員で、事あるごとにこのグータッチをするようにしました。休憩に行くときも、戻ってきても、全員とグータッチ。強制グータッチ状態です(笑) でも、これが互いを近づけ、心の中のわだかまりをなくすきっかけになりました」

また、挨拶も「おはよう」や「お疲れ様」はなく、すべて「ありがとう」に統一することにしたと言います。これについては、一風堂の河原成美社長が「一億杯のありがとう」という言葉を使っているのを見て取り入れたのだそうです。その結果、思わぬ相乗効果が生まれました。
「保険会社時代に鉄鋼業界のお客様がいて、挨拶はすべて『ご安全に』でした。日頃の標語、つまり理念がそのまま挨拶になっていたのです。グータッチと『ありがとう』の挨拶は、キツイことを言わなくてはならない仕事の現場で言いっぱなしにせず心のフォローアップができたということだけでなく、思いのほか業者さんからの受けがよく、徐々にいろいろなところで会社の評判がよくなっていきました。すると業者の方々やスタッフも、メゾンカイザーのお客様になってくれたのです」
***
職人気質の強い現場では、ともすれば言葉が強くなり、心では悪いと思っていてもフォローできないケースが多く見受けられます。そこで木村氏は、負担が少ない簡単なコミュニケーション方法を導入することで理念を浸透させ、スタッフみんなの心をひとつにまとめていきました。
働く人々の価値を合わせるというと、つい難しく考えがちですが、実行するためには、むしろシンプルな方法の方が長続きするものです。
セミナー当日は、あらゆる組織にも落とし込めるよう“価値合わせ”をテーマにグループワークも実施しました。時間を過ぎても熱い議論は続き、“いかに価値を合わせるか”が業種を問わず、職場の命題になっていることが浮き彫りになりました。
グループワークを受けての質疑応答はより熱を帯び、「生まれも育ちも何もかも違う者が集う場所、それが職場。ゆえに価値観を共有することの難しさは今も感じているし、悩みでもある」と、木村氏が心情を吐露する場面も。それでも、基本となるのは「続けられるコミュニケーションであること」だと言います。木村氏との密度の濃い対話により、受講者の皆さんにとって、よりよい組織内コミュニケーションについての理解を深める会となりました。
パイオニアセミナーは年間通じ、定期的に開催しています。今後の詳細は、こちらをチェックしてください。