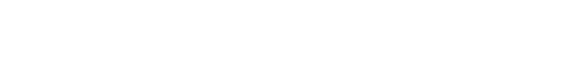視聴者を魅了するスポーツ中継への挑戦。中継のプロが産み出した哲学とは?

2019年7月23日に実施したパイオニアセミナーでは、数々の前例のないテレビ中継を実現してきた株式会社WOWOW 代表取締役社長の田中晃氏をお迎えしました。
不可能を可能にするために生み出された哲学やモチベーションとは?
株式会社WOWOW
代表取締役社長 田中晃氏
1979年早稲田大学第一文学部卒業。日本テレビ放送網株式会社に入社し、箱根駅伝、世界陸上東京大会、トヨタカップ、プロ野球などあらゆるスポーツ中継に携わり、編成部長、メディア戦略局次長等を歴任。2005年にスカイパーフェクト・コミュニケーションズ(現スカパーJSAT)の執行役員常務に就任し、Jリーグ全試合中継の実現やパラリンピックの中継に力を注いだ。2015年に株式会社WOWOW代表取締役社長に就任、現職。2019年3月に著書『準備せよ。スポーツ中継のフィロソフィー』(文藝春秋)を出版。
|「箱根駅伝」中継秘話から学ぶ、前例のないことを実現するのに必要なこと
田中氏のテレビマンとしてのスタートは、大学卒業後に飛び込んだテレビ業界。入社した日本テレビで配属されたスポーツ局で出会ったのは、まさに筋書きのないドラマでした。それを機に田中氏は、スポーツ中継の魅力にどんどんはまっていったといいます。
中でも、1987年から始まった「箱根駅伝」の中継に総合ディレクターとして就任したときの経験から、誰も成し遂げなかったことを実現するために会得したことについて語られました。
箱根駅伝は、大正9年から始まり、1950年代にNHKのラジオ放送がスタート。日本テレビがテレビ中継を手がけた当初から圧倒的な視聴率を誇っていたが、今では平均視聴率31.4%、しかもレースがスタートする前から視聴率20%をマークするようなとんでもない“お化け番組”となっている。
当時、NHKでは技術的な問題でテレビ中継が難しかったため、断念せざるを得ない状況でした。そこで手を挙げたのが日本テレビで、その準備は1年前から始められました。すべてが初の試みであった制作秘話について、当時を振り返る田中氏。

「会場周辺の高い建物を見つけては屋上に上がらせてもらうなど、あらゆるテストを繰り返しました。箱根の山で電波を通すには、カメラを積んだ中継車から送信した電波をヘリコプターが拾って伝送するため、山中にたくさんカメラを置いても中継にはなりません。天候や気流などでヘリコプターが飛べないときもあるので、山の上にも中継地点を構えます。ただ、中継車からは山の頂上が見えないので、テストやシミュレーションを繰り返し、中継車がどこにいてもマイクロマンが山の上の中継地点の方角がわかるようになるまで徹底して準備を重ねました」
この話を聞いただけでも途方もない苦労が伺えますが、この前途多難な中継をサポートしてくれたのは、ほかならぬ沿道の住民の存在だったといいます。カメラの設置場所として屋上を使用させてもらえないかと、あるマンションに飛び込みでお願いにいったときには、来てくれないかと待っていましたという言葉をかけてもらい、以来現在まで31年間そのマンションから撮らせてもらっていたり、箱根町の皆さんは、役場も含めて町をあげてあたたかくサポートしてくれています。
そしていよいよ迎えた箱根駅伝の中継開始の初年度、過酷な労働環境の中、一番の課題は2区間のレースをどう表現するかということに注がれました。この経験に基づく大切な気づきについて、田中氏は次のように語りました。
「数百人のスタッフが主要な箇所に配備され、お借りした現場施設で布団を並べて雑魚寝し、13食連続で冷たい弁当しか食べられないという過酷な状況で業務を遂行することとなりましたが、誰1人として不満を言いませんでした。それは、テレビマンとして誰もやったことにないことへのチャレンジという高いモチベーションがスタッフを支えたからだと思います」
前例のないことを実現するための「チーム力」と「モチベーション」の重要性が理解できる非常に深いエピソードに、聴講者も深く頷き共感していました。
加えて、田中氏は制作する上でのコンセプト作りへのこだわりについても以下のように語りました。
「箱根駅伝の中継には“コンセプトメイク”が重要で、それなしには視聴率は得られません。
徹底的にシード権や区間賞にこだわり、選手への取材を重ねました。それから重要だったのは、たすきをつなぐことの重さでした。OBに取材すると、誰もが子どものように目を輝かせて、ある人は泣きながら当時を思い出しながら話してくれました。一方で、たすきをつなげられなかった人は、みな一様に口をつぐみます。それくらい、たすきをつなぐということは重い経験だということがわかりました。
こうした中継や取材を通じてわかったのは、箱根駅伝は個人のドラマであり、挫折や無念などが延々と積み重なってできている大会だということです。それをいかに具現化できるかということが、日テレの箱根駅伝中継のフィロソフィーとなりました」
フィロソフィーをチーム全員で共有することで、「ドラマの始まりと終わりである“たすき結び”は誰一人としてカットしない」、「大学名だけでなく可能な限り選手名を実況する」「選手の背景を徹底的に取材し、可能なかぎりチープな修飾語を使わない」などといった制作方針が築かれていったといいます。
|あえて遠いゴールを設定することで成功したJリーグ中継

日本テレビを退職後、スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(現スカパーJSAT)の執行役員常務として就任した田中氏。2007年から10年間、Jリーグ全800試合の中継を手がけて、会員数の増加や広告収入などの大きな成功を収めました。
このときも田中氏は、箱根駅伝の中継同様、ビジネスを進める上でのビジョンや基本方針を明らかにすることに注力します。このときに打ち立てた方針は、ビジネスライクに放映権を取得して単に放映するのではなく、「なんのために中継するのか?」という思いを共有することだったといいます。
「Jリーグをはじめ、各チームのサポーターや本拠地のみなさんに、スカパー!も同じ思いを共有する仲間だと思ってもらうことが重要だと考えました。なんのために中継するかといえば、『地域貢献』です。Jリーグ発足の意義は、“スポーツ文化の拠点となり、地域の人々にその喜びを増やしていく”ことにあるからです。だからこそ中継は、地域のサポーター⇒クラブ⇒Jリーグ⇒日本サッカー⇒スカパー!の順序で大切にしていこうと考えました」
こうした基本方針のもと、田中氏は全国のJリーグのクラブに行脚をし、スカパー!の営業活動として、観客の40%をスカパー!の会員にするという目下のビジョンを伝えました。しかし当時の動員数の40%では赤字となるので、そこから観客動員を増やすための施策として、ローカル店の宣伝や自治体との取り組みを開始したといいます。そしてプロジェクトのゴールは日本代表がW杯でベスト4に行くこと、と据えました。
Jリーグプロジェクトを振り返り、ビジネスを円滑に進める上で大切なことについて、田中氏は次のように指摘します。
「一メディアがこれほど入り込み、情報を共有したプロジェクトはほかにはなかったと思います。プロジェクトのゴールを設定するとき、Jリーグの観客が増えて、スカパーの加入者が増えること、日本代表が活躍することなど、社内でもさまざまな議論がありました。どんなビジネスにもゴールはあります。今あらためて言えることは、ビジネスで目標設定をするとき、最終ゴールは遠い方がいいということです。その方が、高い志を持ってモチベーションを維持できるからです」
|東京2020オリンピック・パラリンピックはどんなレガシーを後世に残せるか?

東京2020オリンピック・パラリンピックまであと1年となる中、田中氏は、その時のスポーツ中継のありかたについて熱く語りました。
「東京2020オリンピック・パラリンピックの中継をするうえでまず考えるべきなのは、どんなレガシーを子どもたちや社会に残せるか?ということだと思います。この大会は、今後の日本であらゆる多様性を尊重し、真の意味でインクルーシブな社会を創る絶好の機会です。子どもたちが大きくなった未来の社会が、どんな人も活き活きと生きられる社会になっていたとして、『それはあの満員のスタジアムから始まっているんだよ』と大人たちが教えられれば理想的だと思います」
2008年に田中氏が在籍していたスカパー!がパラリンピックの北京大会の中継を始動。初の試みを前に、社内外からは、「コンテンツとして成り立つのか?」などと不安の声も上がり、さまざまな躊躇や葛藤がある中でスタートしたといいます。当時の心境を田中氏は振り返ります。
「通常のスポーツ中継の場合、プレイヤーのプロフィールや目標などが入りますが、障がい者の場合はその経緯が重く、当初は実況中継する側もその紹介に躊躇がありました。また多様な肉体をそのまま撮ることに対しても遠慮がありました。障がい者スポーツの中継をする側のさまざまな心のバリアがあったのです。」
現在WOWOWの代表取締役社長として、田中氏がWOWOWがIPC(国際パラリンピック委員会)との共同プロジェクトでパラアスリートたちに迫るスポーツドキュメンタリーシリーズ「WHO I AM」への思いについて語りました。
(リンク)https://youtu.be/odt4al-4MuQ
「『WHO I AM』に登場する世界最高峰のパラアスリートたちは様々な障害がある選手です。そんなトップ選手がメダルを取れるかということに主眼を置くと伝えられない魅力があります。彼らの「これが自分だ」という圧倒的な輝きを伝えることが大切な要素。そして、『WHO I AM』は放送にとどまらず、2020年で終わるものではないと思っています」
ここで重要なのは、2020年がゴールではなく、これ以降、いかにダイバーシティがある社会が創られるかということだと強調する田中氏。そのゴールに近づくために、様々なNPOやNGO、パラリンピックの選手らとイベントを開催するなどの取り組みについても紹介されました。
「パラリンピック中継が20年後の日本の担い手である子どもたちを魅了するようなものであってほしい」と田中氏。最後に会場に次のように問いかけ、セミナーを締めくくりました。
「近年、企業の障がい者雇用に関する法律が定められるなど、多様性のある社会に向かいつつありますが、これまでのチャレンジを通じ、日本社会がどうあるべきということが、私自身のゴールにつながっていることがわかってきました。みなさんもこれからどんなゴールを目指し、明日から行動を変えていくかということを考えるきっかけになれば幸いです」
*
*
田中氏が放つ、「フィロソフィーを考え尽くす」「それを全員が共有する」「細部まで具現化する」という3つのメッセージが体験を通じてしみじみと伝わってくるセミナーでした。
誰も実現したことのないことを成し遂げるには、困難がつきものです。
そんなときこそ、田中氏のメッセージは重要な意味を持つはずです。多くのビジネスパーソンが新たなチャレンジをするときにも通ずる重要なメッセージとなりました。
パイオニアセミナーは年間通じ、定期的に開催しています。今後の詳細は、こちらをチェックしてください。