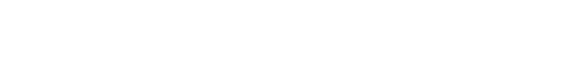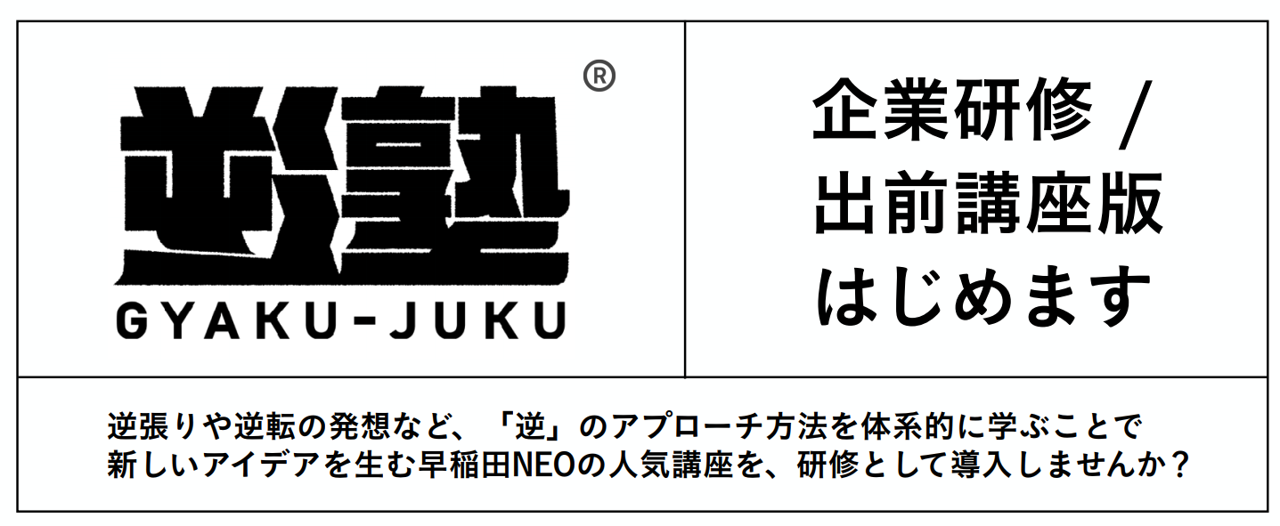サスティナブルに成長するビジネスを目指して

深刻な人口減少、そして労働人口の減少。そんな状況下ではいかに人材を確保し、ビジネスを成長させていくかということが、どんな業界にとっても至上命題となっています。
今年最後のパイオニアセミナーにお迎えしたのは、外食不況の煽りを受けて業績が低迷していたロイヤルホールディングスを、6年連続で増収増益に導いたキーパーソン、ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長の菊地唯夫氏。
金融マンから異ジャンルの外食産業に転身した菊地氏。だからこそ見えてきた、「持続可能なビジネスモデルの仮説と検証」とはどういったものなのでしょうか? 講演から抜粋してお伝えします。
(プロフィール)
ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長
菊地唯夫
早稲田大学政治経済学部卒業後、日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)に入行。1993 年フランスESSEC 経済商科大学院大学(ビジネススクール)卒業。2000 年ドイツ証券会社東京支店入社。2003 年に同社投資銀行本部ディレクターに就任。2004 年ロイヤル株式会社(現ロイヤルホールディングス株式会社)入社。2010 年同社代表取締役社長に就任。2016 年代表取締役会長兼CEO。2019 年から現職。2016 年から 2 年間、日本フードサービス協会会長を務める。サービス産業生産性協議会幹事。
未曾有の人口減少が課題の日本は、アジアから大注目のモデルケース
冒頭で菊地氏は、つい先日、北京の外食セミナーで講演したエピソードについて語りました。菊地氏を驚かせたのは、会場の熱気。1000人以上の飲食店経営者が詰めかけ、何かを学びとろうという熱意に溢れていたといいます。
「実は、中国は日本同様に生産年齢人口が減り始めていて、参加者たちは口を揃えて、『今何をすればいいか?ということを学べるのは日本しかない』と言っていました。つまり、私たちは少子高齢化、人口減少の先進国であり、アジアのモデルケースとして注目されているのです。だからこそ、私たち自身がこの課題に向き合い、仮説・検証・実証していく必要があります」
ロイヤルホールディングスの社長に就任早々、菊地氏のミッションは、まさにそうした厳しい状況下で赤字から脱却し、増収増益を目指すことにありました。
店舗数を減らし、既存店への徹底投資でお客さまの満足度を底上げ
現在、年商1377億円を誇るロイヤルホールディングスは、ロイヤルホスト、天丼てんや、シズラーなどの飲食店を運営。また、空港内、SA・PAなどの飲食店の出店といったコントラクト事業や航空会社の機内食を調製・搭載する機内食事業、ホテル事業としてリッチモンドホテルを運営しています。
外食市場規模がピークを迎えた1997年から、私が社長に就任した2010年までのグループの業績推移をみると、増収増益がありませんでした。市場が縮小する中、既存店の売上は前年割れを起こし続けていたこの14年間、新店を出して売上は上がるも利益は下がる、新店をやめて利益は上がるも売上は下がるといった増収減益、減収増益を繰り返していたと説明する菊地氏。
そこで菊地氏は長い時間軸で目指すべき方向をつくるため、10年間の経営ビジョンをつくり、持続性のある増収増益を目指す策を打ち立てました。
菊地氏が目指したのは、“日本で一番質の高い食&ホスピタリティグループ”。それを達成するために実行してきたことについて、次のように語ります。
「今ある事業の特徴を整理し、事業毎に優先的なミッション、役割を明確にしました。優先順位の1番として、ロイヤルグループのブランドの源泉にすえたロイヤルホストブランドの再構築に着手しました。これまでは、外食市場が縮小するなかで、将来の利益につながる新店にしか投資せず、既存店が前年割れを続けるという負のスパイラルを続けてきましたが、入ってきたお金は既存店再投資に集中し、今来ていただいているお客様の満足度を上げることに集中しました」
店舗数を減らす代わりに、既存店には徹底的に投資したといいます。そこで2012年から既存店の前年売上を超える店舗がグループ全体の50%を超えはじめ、キャッシュフローが安定し、さらなる再投資ができるようになり、それが連続したことで、2011年から6年連続で増収増益を達成。
また、「成長エンジンの育成」のミッションを与え、成長に貢献したのは、高齢者に人気で日常のメニューとして飽きられにくい「天丼てんや」でした。高齢者が売上増に寄与したわけです。しかも日本食として人気の高い天ぷら主体の業態はインバウンドにも強いブランドです。
外食産業の難しさについてあらためて振り返る菊地氏。
「ある時、データを見ていてこれまでの業績の回復は我々の戦略だけが当たっていたわけではなく、追い風が吹いていたのではないかと感じました。私の仮説ですが、要因としてあげられるのはこれまで消費をリードしてきた団塊世代の志向性ではないかと思っています。2013年から団塊の世代が65歳を超え始めたことで、年金をもらえるようになり、少し安心して購買力が増えたのではと考えています。実はロイヤルホストの業績の回復は百貨店と同じタイミングでした。百貨店とファミリーレストラン、それぞれの全盛期に元気だった団塊世代の方々の消費が上がってきたタイミングと私どもの施策が合致した、そうした外部環境も大きかったのではないかと思います」
こうした仮説をたてて検証していくことは重要です。そしてこの例は、これまで消費をリードしてきた世代の消費が下がれば、次の世代の消費はあまり期待できないため、今までのパターンが今後も踏襲されるとは限らないのは注意が必要とも語りました。
今の時代に合った、サスティナブルな外食産業を創るために
ファミリーレストランの草分け的存在「ロイヤルホスト」の創業者・江頭匡一氏は、かつて「外食を産業にする」ことを目指しました。それを実現したのは、人口増加、GDPの成長を背景に増加するニーズに対応するため、産業化の王道である、画一性、効率、スピードで、チェーン化やセントラルキッチン方式などでした。
経済が成長していた時期は、これらの手法が功を奏しました。しかし、現在では状況が違います。人口は減少し続け、常に効率性が求められてきた飲食業界でも人材の確保は大きな課題です。そのような課題のなか、サスティナブルな外食産業のあり方とは何か?ということを模索し続け、菊地氏は、近年外食産業で騒がれた、賞味期限問題、異物混入といった諸問題の根底にあるものをあらためて見つめ直します。
「製造業はコストカットのため、海外に工場を移すなどの対応を講じてきましたが、外食では同じ方法はとれません。自分たちでコントロールできるコストである原材料費や人件費を圧縮した結果が産業化のひずみを生み出し、限界が出始めているのではないかと思うようになりました」
また、不確実性の時代といわれる中で確実なこと=「日本の人口減少」と「世界の人口増加」は、これからも国内の生産性を引き下げる方向に働き、その下がるエスカレーターはますます加速すると分析します。
一方で、サービス産業で生産性を上げることは、人を減らすことではないと強調する菊地氏。サービス産業においては、“サービスの提供と消費の同時性”があるから安易に人を減らすことはできないようです。
そのジレンマを解消すべく、菊地氏が考え抜いて立てた仮説が、「今後のホスピタリティビジネスの産業化」でした。それを実証すべく取り組まれたことを語ります。
「昨今はお客さまが喜ぶ業態を作ったものの、人材が確保できず、店のオープンを延期せざるを得ないことも珍しくありません。外食市場が縮小している上に人材の確保も難しくなっている中、これまでの「規模の成長」だけではなく、「質の成長」による産業化もあると考えました。それがロイヤルホストの24時間営業の廃止や店舗休業日にも結び付く考え方です」
ロイヤルホストは早朝、深夜の営業時間短縮を検討した時に試算した売上損失は年間7億円。かなり思い切った改革といえます。しかし早朝、深夜の営業を短縮した代わりランチとディナーの質を高めたところ、逆に1年で売上げが増えるという結果に。そこで次の年には年3日の店舗休業日を作りました。
この経験を振り返りながら、外食産業において課題となり、重要視される「付加価値」について次のように言及しました。
「日本ではおもてなしの期待値は非常に高いのに対し、サービスに対しての対価は低いのが現状で、このサービスを産業化するのは難しい。昔は高いといわれた日本の外食は、このところ後進国の人から、『日本の外食はなぜこんなに安いのか?』と聞かれることもあります。でも実際は、この数十年のうちにコストを安くするための技術革新はほとんど起きていません。チップが飲食費の外側にあるアメリカなどとは違って、昔は価格に含まれていたサービスの対価がデフレに引きずられてなくなっていったのではないかと思います」
外食産業における付加価値とは、「ぜいたくなひととき」「健康志向」「希少性」などで、これらがあれば多少高くてもいいと思えること。付加価値の演出を実証する、最近のロイヤルホストでの取り組みについて紹介いただきました。
「規模が大きくなればなるほど付加価値を演出するのは難しくなります。約220店舗のロイヤルホストではここ数年、国産食材を使った料理フェアを行っています。国産の食材は量が手配できませんので使える食材やサービスの限界があるなかで、価値を最大化しようという取り組みです」
テクノロジーの活用で、サスティナブルで新たな外食産業を目指す
さらなる新たな改革として、テクノロジーの活用で外食産業のひずみを解決するために行っている事例を紹介。
まず、菊地氏はアメリカのレストラン売上トップ200企業のグラフを提示しました。
マクドナルドを筆頭に上位に目立つのは、オートメーション化しやすいファストフード店ばかりです。かといって業態問わず闇雲にテクノロジーを取り入れるのではなく、バランスが重要だと菊地氏は強調します。
「飲食業は、“アート”(感性、エモーション、手作りといった価値)と“サイエンス”(論理性、システム)のバランスが難しい産業です。どっちに偏り過ぎてもダメなのです」
実際にテクノロジーの活用実験を始めたのは、研究開発店舗としてオープンした「GATHERING TABLE PANTRY」での事例。働き方改革と生産性の両立だけを考えて、接客以外のすべてをロボットやテクノロジーに置き換えるとどうなるかを研究したそうです。
そこでは、ボタンひとつでメニューにあわせておいしく加熱調理できるようプログラミングされた、パナソニックと共同研究したマイクロウェーブコンヴェクションオーブンを使用。また、レジ締めなどの開閉店作業・掃除・管理事務といった作業も機械化されているとのこと。その目的について菊地氏は次のように紹介します。
「人がすることで価値を生み出す作業に人を集中させ、それ以外の作業をすべて機械化によって圧縮する試みです。この結果、これまでグループ内の多くの店舗で約40分かかっていたレジ締めは5分に短縮することができました。また、この店舗はリアルなオープンイノベーションのプラットフォームとして機能させています。この店舗があることで、グループ全体において他業界とのコラボレーションや産学連携で新しい決済手段を実験したり、食器配膳ロボなどを開発・展開したりするなど、新たな可能性を追究しています」
最新テクノロジーの導入やITの実験場の事例とあわせて語られたのは、「テクノロジーは接客する人の仕事を奪うのではないか?」という不安への持論でした。
「労働は大きく分けて『肉体労働』『頭脳労働』『感情労働』の3つがあると言われています。テクノロジーが発展するこれから先、肉体労働はどんどんロボット化され、頭脳労働の代わりにAIが活躍するかもしれませんが、感情労働だけは変わりません。テクノロジーによって、人間はこれまで以上に人が共感するサービスに集中でき、サービスと生産性の同時性のジレンマを解消することにつながるのではないでしょうか」
持続可能なビジネスモデルを求めつづけられた菊地氏は、人材を活かすことの重要性と将来性について語ってくださいました。
異ジャンルに飛び込み、改革の抵抗勢力を突破するには?
そもそも異ジャンルから転身し、社長に就任した当時、少なからず社内でやりにくい空気を感じていたという菊地氏。後半の質問タイムでは、そうしたなかで、いかに改革をしてきたかについて、受講者から質問がありました。
菊地氏は、現場経験もまったくない上に、当時のロイヤルホールディングス幹部の平均年齢が62歳というなかで、44歳の若さで社長になり、当時はあまり求心力がなかったことを前置きした上で、次のように答えました。
「なにか私が新しいことを始めても、幹部のメンバーからしてみたら、『余り意味がないのではないか』というのが大方の空気でした。ところが、私が従業員に向けて会社のビジョンや改革についての決算説明会を定期的に始めたら、やる気のある従業員たちが大勢集まるようになりました。気づけば、経営幹部よりも従業員たちの方がよっぽど会社や現場について理解している状況になっていました。そうした従業員たちの動きに刺激された幹部たちが、次第に決算説明会やそのほかの勉強会に出席するようになり2年ほど経つと雰囲気もすっかりかわりました」
強権的な働きかけをするのではなく、意識の高い従業員に支えられ、時間をかけながら社内を変容させていったようです。トップ自らさまざまな説明会や勉強会を開催し、メッセージを伝える地道な努力の成果が伺えます。
そのほか、これまで離職率が高かったロイヤルホールディングスの離職率が低くなったゆえん、人材確保や育成、世代間ギャップの埋め方など、多くの業界にも共通する課題に関して多岐に渡る質問が寄せられる中、大盛況のうちに会は終了しました。
人口減少社会をいかに生きるかということは、社会全体の課題であり、これからのあらゆるビジネスにも影響する重要事項です。
その煽りを受けやすい外食産業のトップリーダーの思考とチャレンジは、多くの人に勇気をもたらすものとなりました。
*
パイオニアセミナーは年間通じ、定期的に開催しています。今後の詳細は、こちらをチェックしてください。